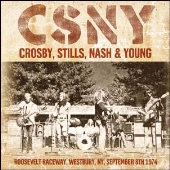ふと気づいたら、一度もCD化されていない『The Beach Boys’ Christmas Album』のモノラル盤がダウンロード販売していたので、退院までの間に購入し、帰宅後チェックをしたところ。確かにこれは「真正モノ」であり、後のCD化で編集され長くなった「偽モノ」は混じっていない。音像の好みなどは除外する。もともと私はモノ派ではなくステレオ派、モノの方がいいかなと思う曲があるのは一般的には1963年と1964年くらいまでの音源だ。購入はiTunesのMono&Stereo1900円版。現在では疑似ステレオしかない『Surfin’ Safari』『Wild Honey』のステレオ、まったく違いが無い『Beach Boys Concert』のモノラル(予想通りこれだけモノラルリリースなし)を除くとモノラルが無くなった『Friends』までは、全てステレオ、モノラルの両仕様が出て、以降のアルバムは『The Beach Boys(1985)』までステレオの「ハイレゾ版」が出ているのだ!さらにAnalogue Productionsからのステレオ、モノラル別々にハイブリッドSACDと200gアナログLPの発売、ここも前述したように『Holland』を皮切りにブラザー時代以降も網羅するだろうから、いったい全部揃えたら幾らかかるのか!私のように3年半に渡る病人、もう定年まで2年なのにこれからゼロからリハビリして1年後に奇跡が起きて再復職という非現実的は諦め、もう勧奨退職して社会保険は妻の扶養に入り、退職金で住宅ローンを完済して残りの治療費に…という人間に、そんな高額商品を揃える余裕はなくなった。一騎当千のビーチ・ボーイズ・ファンの方、これらの全音源の違いがあれば是非教えて欲しい。楽しみにお待ちしています。
それではようやく、『The Beach Boys’ Christmas Album(Mono & Stereo)』の違いについて紹介しよう。
- 「Little Saint Nick(Album Version)」…鈴と鉄琴が入っていないステレオのアルバム・ヴァージョンは『Ultimate Christmas』や、90年代にリリースされたボーナス・トラック付『The Beach Boys’ Christmas Album』で聴けたが 初CD化のモノ・ヴァージョンは最後のリフレインがステレオの3回(1分59秒)に比べて2回(1分52秒)でフェイドアウトしてしまう。
- 「The Man With All The Toys」…ステレオのエンディングは2回目のリフレインの最後の高い「オ!」のあとのギターで終わってしまうが、初CD化のモノラルはさらに2秒長く、3回目のリフレインの「オ!」を2回聴くことができる。90年代の『The Beach Boys’ Christmas Album』や、『U.S. Singles Collection Capitol Years 1962-1965』はモノで入っているが、ステレオと同じく短く「悪い偽モノ」編集されていた。
- 「Santa’s Beard」…ステレオはモノラルより3秒長く、最後のア・カペラ風のHe’s Just Helpin’ Santa Clausの歌の部分を聴くことができる。この点はLPとCDと扱いは変わらず、以前より変わらない。
- 「Merry Christmas Baby」…モノ・アルバムのヴァージョンは初CD化だが、これは悲しいシロモノ。というのは間奏のハミングの後の歌が始まってすぐにフェイドアウトしてしまって、続きの歌とリフレインがまったくカットされてしまっているからだ。だからステレオに比べ18秒も短い。なお、この音源には注意点があり、90年代にリリースされたボーナス・トラック付『The Beach Boys’ Christmas Album』では、そのボーナス・トラックを除くと、「Little Saint Nick(Album Version)」のみステレオで、他のオリジナル曲はモノラルで作られていた。しかしここでの「Merry Christmas Baby」CD化の際に、最後のリフレインがステレオは4回で終わっていたが、このCDのモノラルは6回目の頭で終わり、ステレオよりさらに5秒長くした。よってLPのモノラルよりも23秒も長いという新編集のCD用のモノラル(冒頭で「偽モノ」と書いたがいい偽モノだ)なので持っていない人は入手しておこう。
- 「Christmas Day」…初CD化の「真正モノラル」は、ステレオ(CD、LP)に比べ6秒長く、最後のAnd I'll Never Outgrow The Thrill Of Christmas Dayまで聴くことができる。それまでのCDのモノラル(前述のCD)はステレオよりは長いがAnd I'll Never Outgrow Thrill…で終わる「偽モノ」だった。
- 「We Three Kings Of Orient Are」…ステレオ、モノ共、LPもCDもエンディングをフェイドアウト気味に絞っていくので最後のコーラス非常に小さい。なお、この音源にも注意事項があり、90年代にリリースされた『The Beach Boys’ Christmas Album』のCDのモノはフェイドアウトしない編集に変えた「いい偽モノ」なので最後のハーモニーまでしっかり聴くことができる。
※その他のアルバム曲は、完奏するので、CD、LPも含め、ステレオとモノラルとで差はない。最後に同時期のシングルオンリー&別テイクのステレオとモノを紹介しておこう。
「Little Saint Nick(Single Version)」…ステレオは3ヴァージョンあり、まず『Ultimate Christmas』のヴァージョンは2分6秒と最長で、他では聴けない4回目のリフレインでブライアンの上昇するアドリブヴォーカルを楽しめる。鈴と鉄琴の音は分離よく聴こえ適度の大きさ。日本独自編集で現在リイシュー中の『ビーチ・ボーイズUSシングル・コレクション』のヴァージョンは鈴と鉄琴の音がかなり大きくミックスされ長さは2分2秒。『U.S. Singles Collection Capitol Years 1962-1965』収録の2008 Stereo Mixは、モノラルのシングル・ヴァージョンに似せていて、ヴォーカルが大きく、鈴と鉄琴の音は小さくミックスされ長さもモノラルと同じ1分57秒である。多くの『The Beach Boys’ Christmas Album』や『Christmas Harmony』など「Little Saint Nick」が1テイクしか入っていないCDはアルバム・ヴァージョンではなく、モノ・シングル・ヴァージョンが収録されている。
「The Lord’s Prayer」…1963年の「Little Saint Nick」のシングルB面曲で、アルバム未収録。元はモノラルで『U.S. Singles Collection Capitol Years 1962-1965』や前述の日本終版『ビーチ・ボーイズUSシングル・コレクション』、『The Capitol Years』、『Rarities』等に入っているがなぜか『Ultimate Christmas』には収録されなかった。ステレオは90年代の『The Beach Boys’ Christmas Album』のボーナス・トラックに、ステレオ・リミックスは『U.S. Singles Collection Capitol Years 1962-1965』『Hawthorne CA』で登場したが、特に違いは無い。ステレオとステレオ・リミックスの違いもほとんどない。
「Auld Lang Syne(A Cappella)」…デニスのナレーション抜きのこの素晴らしいア・カペラはモノラルで90年代の『The Beach Boys' Christmas Album』のボーナス・トラック、『The Capitol Years』、『Rarities』で聴くことができる。後に冒頭にカウントが入ったステレオ・ヴァージョンが『Ultimate Christmas』で登場した。
「Little Saint Nick(Alternate Version)」…「Little Saint Nick」というより「Drive-In」の歌詞を変えただけといっていいボツヴァージョン。モノラルは90年代の『The Beach Boys’ Christmas Album』、ステレオは『Ultimate Christmas』で登場。ダウンロード販売のみの『Keep An Eye On Summer』では歌の途中までの練習後に本番テイクが入っている「Little Saint Nick(Drive-In)(Vocal Session Highlights And New Stereo Mix)」が収録された。
その他ではその『Keep An Eye On Summer』に、ビーチ・ボーイズの演奏ではないがクリスマス・アルバムのためにディック・レイノルズが録音していた「Christmas Eve」と「Jingle Bells」のオケがあって驚かされた。アルバム用にまだ用意されていたのか。(佐野邦彦)